| Excel Reference Manual | Home | ExcelVBAPartsCollection | DownLoad | My Profile | ||
| Menu | Back | Next | Links | Excel Function Manual | Myself | My BBS |
| 計算式に使用する演算子 |
| セルの参照形式 |
| 一般の計算式入力 |
| オートSUMで自動集計 |
| 関数の入力 |
1 Excelで使用できる演算子 |
|
演算子とは、数式がどのような演算(計算や比較)行うのかを決める式の要素のことをいいます。Excel
の数式で使用できる演算子は下記のとおりです。 |
|
分 類 |
機 能 |
|---|---|
| 算術演算子 | 数値を組み合わせて計算を行い、計算結果は数値になります。 |
| 比較演算子 | 演算子の左辺と右辺の数値を比較します。又、セル参照の計算結果として返された数値を比較できます。比較の結果は「True(真)」又は「False(偽)」になります。通常は、IF関数の引数として利用されることが多い |
| 文字列演算子 | 「&」(アンパサンド)の1つだけであり、複数の文字の結合や、連結して1つの連続する文字列に変換するときに使用します。文字列化した数値やセル参照も結合することができ、結果は文字列として表示されます。 |
| 参照演算子 | 数式や関数でセル参照を実行するときに使用します。 |
2 演算子の種類と優先順位 |
||||
| Excel での演算子と優先順位(式の中で実行される順序)及びその機能は、下表のとおりです。なお、同一優先順位欄に複数の演算子があるのは、各々が同格であることを表しています。 | ||||
演算子の分類 |
優先順位 |
演算子 |
機 能 |
実 例 |
|---|---|---|---|---|
| 参照演算子 | 1 | [ : ] | コロン。2つのセル番地の間に入力して、その2つのセルを含めた「セル範囲」の参照を指定する。 | A1:D5 |
| [ , ] | カンマ。複数のセル番地の間に入力することで、セルの複数選択の参照を指定する。 | SUM(A1,D5) | ||
| 算術演算子 | 2 | - | 負号(マイナス) | -5 |
| 3 | % | パーセンテージ(パーセント記号) | 30% | |
| 4 | ^ | べき乗(キャレット) | 2^(2*2) | |
| 5 | * | 乗算(アスタリスク) | 2*2 | |
| / | 除算(スラッシュ) | 4/2 | ||
| 6 | + | 加算(プラス) | 2+2 | |
| - | 減算(マイナス) | 4-2 | ||
| 文字列演算子 | 7 | & | 文字列の結合(アンパサンド) | A&B・・・AB |
| 比較演算子 | 8 | = | 等号(左辺と右辺が等しい) | A1=B1 |
| < | 未満(左辺は右辺より小さい) | A1<B1 | ||
| > | 超える(左辺は右辺より大きい) | A1>B1 | ||
| <= | 〜以下(左辺は右辺以下) | A1<=B1 | ||
| >= | 〜以上(左辺は右辺以上) | A1>=B1 | ||
| <> | 不等号(左辺と右辺が等しくない)。 | A1<>B1 | ||
1 計算式の参照形式と機能 |
| ワークシートのセルまたはセル範囲を識別し、数式で使う値やデータの位置を指定することを「セル参照」といいます。セル参照は列番号と行番号で表しますが、表示の仕方に「A1
参照形式」と「R1C1 参照形式」の2通りがあります。 また、同じブックにある他のシートのセルの参照、他のブックにあるセルの参照、他のアプリケーションのデータの参照を行うこともできます。他のブックにあるセルの参照を外部参照といい、他のアプリケーションのデータの参照をリモート参照といいます。 |
(1) A1 参照形式 |
| A1 参照形式では、列を文字 (A 〜 IV の計 256 列) で参照し、行を番号 (1 〜 65536)
で参照します。これらの文字と番号はそれぞれ、列番号および行番号と呼ばれます。既定ではA1 参照形式が使われます。 セル範囲を参照するには、範囲の左上端のセル、コロン (:)、範囲の右下端のセルの順に指定します。 |
| [例1] A列25行目の座標名。 A25 [例2] A列1行目が左上端、D列5行目が右下端のセル範囲 A1:D5 |
(2) R1C1 参照形式 |
| R1C1 参照形式では、"R" に続けて行番号を指定し、"C" に続けて列番号を指定してセルの位置を表します。この場合、列番号はA1
参照形式と異なり、A列を1、IV列を256のように数値で表します。 R1C1 参照形式は、マクロで行と列の位置を計算する場合に便利です。 セル範囲を参照するには、範囲の左上端のセル、コロン (:)、範囲の右下端のセルの順に指定します。 |
| [例1] A列25行目の座標名 R25C1 [例2] A列1行目が左上端、D列5行目が右下端セル範囲 R1C1:R5C4 |
2 相対参照・絶対参照・混合参照 |
| 数式が入力されているセルを基点にして他のセルを参照する形式を「相対参照」といい、座標名を相対番地とよびます。特定の位置にあるセルを常に参照する形式を「絶対参照」といい、座標名を絶対番地と呼びます。 相対参照と絶対参照の相違は参照セルを複写したときに現れます。相対参照はコピー元の参照関係がコピー先にも反映されるのに対して、絶対参照はコピーしてもコピー元の参照位置が変わりません。 さらには、相対参照と絶対参照を組み合わせる方法もあり、これを「混合参照」といいます。 |
(1) 相対参照 |
| 相対参照は、別のセルやセル範囲に数式をコピーすると、行番号と列番号の数式との関係は、元のセル参照と数式との関係を維持しながら、新しい数式内の参照関係が自動調整されて別のセルを参照します。 例えば、セルC2に「=A2*B2」という式が入力されているとき、C2の式を計算式入力セルの下(C3)に複写すると、計算式入力セル(C2)から 2 列左(A列)と 1 列左(B列)の同じ行番号のセルの乗算を行うという相対的関係を保持したまま、行番号だけを自動調整して「=A3*B3」というセル参照に変更します。 また、セルB7に「=SUM(B2:B6)」という式が入力されているとき、B7の式を計算式入力セルの右(C7)に複写すると、計算式入力セル(B7)の 1 行上から 6 行上までの同じ列番号のセルの加算を行うという相対的関係を保持したまま、列番号だけを自動調整して「=SUM(C2*C6)」というセル参照に変更します。 つまり、計算式入力セルを同じ行で下に複写すると、セル参照の行番号が移動した行数分自動調整され、計算式入力セルを同じ列で右に複写すると、セル参照の列番号が移動した列数分自動調整されるということになります。 |
| [例1] B2からE2までを加算する式をF2に入力する。 =SUM(B2:E2) 上記の式をF3(下)に複写したときの計算式(行番号が自動調節される)。 =SUM(B3:E3) [例2] B2からB6までを加算する式をB7に入力する。 =SUM(B2:B6) 上記の式をC7(右)に複写したときの計算式(列番号が自動調節される) =SUM(C2:C6) |
相対参照の指定例 |
| 下図のセルC8は、4月の縦合計を求める計算式です。これを右端列までコピーすると、参照セルの列番号だけが自動調節されます。 O3の計算式は、行の横計を求める計算式です。これを最終行までコピーすると、参照セルの行番号だけが自動調節されます。 |
|
|
(2) 絶対参照 |
| 絶対参照は、特定の位置にあるセルを常に参照するため、コピーしてもコピー元の参照関係が変わりません。(行番号、列番号は変化せず、固定される。)参照するセルを調整しないで数式を他のセルにコピーする場合は、絶対参照を使います。 絶対参照を指定するときは、セル参照の前に「$」マークを付けます。 例えば、セルA1を絶対参照で指定するときは、「$A$1」と指定します。 |
| [例1] B2からE2までを加算する式をF2に入力する。 =SUM($B$2:$E$2) [例2] B2からB6までを加算する式をB7に入力する。 =SUM($B$2:$B$6) |
(3) 混合参照 |
| 混合参照とは、相対参照と絶対参照を組み合わせて使用する方法のことをいいます。混合参照は、行番号または列番号だけ固定して複写したい場合に利用します。 列番号だけ固定したいときは、列番号の前に「$」を付けます。また、行番号だけを固定したいときは、行番号の前に「$」を付けます。 $A1・・・列番号だけを固定。 A$1・・・行番号だけを固定。 |
混合参照と絶対参照の指定例 |
| 左上図セルE4の計算式は、単価欄の列番号だけ絶対参照で行番号は相対参照となっています。計算式を右に複写して金額を求めるときに、単価欄の列番号だけを変化させず固定させておくためです。 左下図セルE11の計算式は、単価欄の行番号だけ絶対参照で列番号は相対参照となっています。計算式を下に複写して金額を求めるときに、単価欄の行番号だけを変化させず固定しておくためです。 こうすることにより、それぞれの表に1箇所入力するだけで、縦横すべての複写が可能となります。 右側の表は、上図がVLOOKUP関数の参照となるリスト(コード表)です。下図のコード欄にコード番号を入力すると右列に品名を表示するようになっています。 リスト範囲を絶対参照としてあるのは、セルN9に入力した計算式を下に複写したとき、上図のリスト範囲を変化させずに常に範囲を固定しておくためです。 |
|
(4) 参照形式の切り換え |
| 相対参照・絶対参照・混合参照の切り換えは、「F4」キーで行います。 セルの座標名を入力してから「F4」キーを押すごとに参照形式が自動的に変化します。最初に相対参照形式になっているときに、 「F4」キーを 1 回押す・・・絶対参照 $A$1 「F4」キーを 2 回押す・・・行固定の混合参照 A$1 「F4」キーを 3 回押す・・・列固定の混合参照 $A1 「F4」キーを 4 回押す・・・相対参照に戻る A1 既に入力確定済みのセル座標名の参照形式を切り換えるときは、座標名をドラッグしてから「F4」キーを押します。 |
3 見出しによる参照 |
| 一般的には、ワークシートの各列の一番上と各行の一番左には見出し (ラベル)
があり、これらの見出しを数式で使って、関連するデータを参照することができます。ワークシートの見出し以外にも、データの内容を表す名前を作成して、セル、セル範囲、数式、または定数を参照することができます。 数式で見出しを使用する場合は、予めメニューの [ツール(T)] 、[オプション(O)] を選択し、「オプション」ダイアログボックスの[計算方法] タブをクリックします。 [ブック オプション] の [数式でラベルを使用する] チェックボックスをオンにします。 |
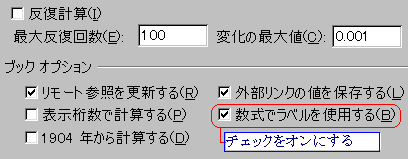 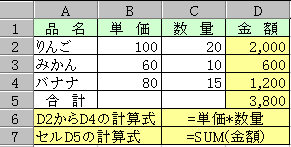 |
4 「名前」による参照 |
| セル、セル範囲、数式、または定数値にその内容を表す名前を付けて参照することができます。 データに見出しがないか、またはワークシートに格納されている情報を他のシートで使用する場合は、セルまたはセル範囲を示す「名前」を作成して参照すると計算式がわかりやすくなります。 「名前」の設定の仕方の詳細は、こちらを参照してください。 下図は、セル範囲に名前をつけて計算式の中でセル参照として利用した例です。 左図は金額欄に「売上合計」という名前を付けて、計算式の合計範囲に使用しています。右図は、中図にある「コード表」のデータ部分に「コード表」という名前を付けて、検索範囲として利用しています。 |
|
|
1 計算式の入力場所 |
|
| 計算式の入力は、セルまたは数式バーで行います。左図上が数式バー、左図下がセルです。 | |
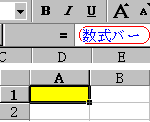 |
(1) セル内での入力 |
| 入力するセルをクリックしてから「 = (イコール)」を入力すると、計算式を入力て゜きる状態になりますので、続けて計算式を入力します。 |
|
(2) 数式バーでの入力 |
|
| 入力するセルをクリックしてから、「数式バー」の左にある「数式の編集」ボタンをクリックすると、数式バー内に「 = (イコール)」が表示されますので、数式バーをクリックしてから計算式を入力します。 | |
2 計算式入力方法 |
| 関数の使用を伴わない一般の計算式は、通常、演算子、定数、セル参照を組み合わせて指定します。 セル参照とは、数式の中で、数値などのデータの代わりに予めデータが入力されているセルの番地(座標名)を入力して、セル内の数値を演算対象とすることができる機能です。 セル番地は、セル内や数式バーで数式を入力している状態でカーソルを置いたま、参照するセルをクリックするだけで数式バー上に自動入力されます。また、他のシートやブックのセル番地も同じ方法で入力し、参照することもできます。 [例 セルA1 に単価(10)、セルB1 に数量(5)が入力されており、セルC1 に消費税込みの金額を求める計算式を入力するには] セルC1 に =A1*B1*1.05 と入力します。 |
|
数式バーに上記計算式を入力する場合のパソコン操作手順は次のようになります。 1. セルC1をクリックします (計算式を入力するセルを指定します)。 2. 数式の編集ボタンをクリックします。 (数式バーに = が入力され、下図の数式パレットが表示されますのでドラッグして邪魔にならないところまで移動してください)。また、関数ボックスに表示されている「VLOOKUP」は、前回使用した関数で、計算式の入力とは直接関係ありませんので、無視してください。 なお、数式の編集ボタンの左側にあるマークは、「×」が取り消し、「v」が計算式の確定を意味しています。) |
|
|
| 3. 数式バーの = の右をクリックします。(ここからが計算式の入力となります)。 4. セルA1をクリックします ( = の右に 参照したセル座標名 A1 が入力されます)。 5. キーボードで演算子 * (アスタリスク)を入力します。 6. セルB1をクリックします ( * の右に 参照したセル座標名 B1 が入力されます)。 7. 演算子 * に続けて、定数 1.05 ( 1 + 消費税率 )を入力します。 8. 計算式の入力がすべて完了すると、数式パレットが下図のようになり、数式の結果が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。 |
|
|
| どんな複雑な計算式でも、式の論理構造に従って上記の操作で指定すれば計算式を入力できます。 |
|
|
|
1 関数の種類と書式 |
|
(1) 関数の種類 |
|
| 「EXCEL」では、関数を性質的に分類して、「財務関数」、「日付/時刻関数」、「数学/三角関数」、「統計関数」、「検索/行列関数」、「データベース関数」、「文字列関数」、「論理関数」、「情報関数」、「エンジニアリング関数」の10種類に区分し、関数入力に際して、文類項目別に関数を検索して入力する方式を採用しています。 | |
(2) 関数の書式各部の名称 |
|
|
|
| 関数の書式は、使用する関数の種類によって異なりますが、概ね上図のようになっています。 ● 引数・・・関数が操作や計算を実行するために使う値のことをいいます。引数には、数式や数式の結果以外の定数(数値、文字列、論理値、エラー値)を指定できます。 ● 引数分離記号・・・通常は図のように「,」(カンマ)を使用しますが、セル範囲を参照する場合などは「:」(コロン)を使うこともできます。セル範囲の参照時にセルをドラッグすると、「:」が引数の間に自動入力されます。 ● 結果・・・関数によって計算された値を「結果」又は「戻り値」といいます。 |
|
2 関数の入力手順 |
|
| 関数を入力する手順を「IF」関数の入力例で説明します。 入力する関数の計算式は下記のとおりです。 計算式 =IF(A1 = "","未入力",A1) 意 味 A1が空白ならば「未入力」を、空白でなければセル「A1」の値を計算式入力セルの値とする。 |
|
(1) 関数入力セル(右図の黄色のセル)をクリックします |
|
(2) 「関数貼り付け」ボタン(右図の赤丸部分)をクリックします |
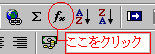 |
(3) 関数名を選択します |
|
| 「関数の貼り付け」ダイアログボックス(下図)で、「関数の分類(C)」欄の項目名、「関数名(N)」欄の関数名を選択して「OK」ボタンをクリックします。 「関数の分類(C)」の項目を選択すると、選択した分類項目に含まれる関数が「関数名(N)」欄に表示されます。下部には関数の書式と機能の説明が表示されます。 関数の詳しい内容を知りたいときは、図の左下隅にあるヘルプボタンをクリックすると、右図のOffice アシスタント(図では犬の絵になっていますが、設定内容によって絵が異なります。)が表示されますので、「この機能についてのヘルプ」の青いボタンをクリックしてください。 |
|
|
|
|
(4) 数式パレットで引数を入力します。 |
|
| 数式パレット各部の名称と機能は下記のとおりです。
薄い色の枠内の表示内容
● 左上隅の「IF」・・・編集中の関数名。● 「論理式、真の場合、偽の場合」・・・引数名。 ● その右にある白いボックス・・・引数編集ボックス。(ここに数式の引数を入力します。) ● 引数編集ボックスの右端にある赤い矢印・・・数式パレット折りたたみボタンで、主にセルやセル範囲を指定するときに使用します。赤い矢印をクリックすると、数式パレットを折りたたんでその引数編集ボックスだけを表示します。再度矢印ボタンをクリックすると数式パレットが元の状態に戻ります。 ● 引数編集ボックス右側の「= TRUE、= "未入力"、= 0」は引数の実行内容。 薄い色の枠の外側の表示内容
● 枠の下にある「 = "未入力"」・・・編集中の関数の実行結果。 ● ヘルプボタン右の「数式の結果 = 未入力」・・・数式全体の実行結果。 |
|
|
|
|
引数の入力がすべて完了したら、「OK」ボタンをクリックします。/td> | |
3 1つの計算式で関数を複数入力する場合の計算式入力(関数のネスト) |
|
| 関数式の中にさらに関数を組み込むことができます。これを「関数のネスト」といいます。 数式には 7 レベルまでのネストした関数を指定することができます。関数 A の引数として関数 B を指定すると、関数 B は第二レベルの関数となります。さらに、関数 B の引数として関数 C を指定すると、関数 C は第三レベルの関数になります。 なお、第一レベル関数 A の複数の引数に、それぞれ関数 B 、関数 C を指定した場合のように、同一関数の複数の引数に関数を指定しても、関数 B、関数 C は両方とも第二レベル関数になります。 |
|
複数の関数を編集するときの関数の切り替え方法 |
|
| 第一レベル関数の引数に第二レベル関数を使用してネストを行う場合、編集中の第二レベル関数の数式パレットでの入力を終えて、再度第一レベル関数の数式パレットに入力をするときなど、関数の切り替えを行うには、数式バーで編集する関数名をクリックすると該当の数式パレットが表示されます。 | |
関数をネストする手順 |
|
| 関数をネストする手順を下記の入力例で説明します。 入力する関数の計算式は下記のとおりです。 計算式 =IF(A1="","未入力",IF(OR(A1<1,A1>12),"誤入力","OK")) 意 味 セルA1が空白ならば「未入力」を、空白でない場合、セル「A1」の値が 1 未満または 12 を超えるときは「誤入力」、それ以外のときは「OK」を計算式入力セルの値とします。 |
|
(1) 関数入力セル(右図の黄色のセル)をクリックします |
|
(2) 「関数貼り付け」ボタン(右図の赤丸部分)をクリックします |
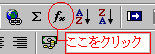 |
(3) 最初の IF 関数を選択します |
|
| 「関数の貼り付け」ダイアログボックス(下図)で、「関数の分類(C)」欄の「論理」、「関数名(N)」欄の IF 関数を選択して「OK」ボタンをクリックします。 | |
|
|
|
(4) IF 関数の引数を入力します。 |
|
| 最初の IF
関数の「論理式」と「真の場合」の式を引数編集ボックスに入力したら、「偽の場合」の引数編集ボックスをクリックします。 偽の場合」の引数に、2 番目の IF 関数を指定するため、「関数ボックス」(赤枠)をクリックして 2 番目の IF 関数の数式パレットを呼出します。 「関数ボックス」には、直前に使用した関数名が表示されています。別の関数を指定する場合は、「関数ボックス右端の▼ボタンをクリックして、関数一覧から選択します。 |
|
|
|
(5) 2 番目の IF 関数の「論理式」に OR 関数を指定します |
|
| 2 番目の IF
関数の数式パレット(下図左)が表示されたら、「論理式」の引数編集ボックスをクリックします。次に関数ボックスの▼ボタン(赤枠内)をクリックすると関数一覧(下図右)が表示されます。 一覧に表示されている関数名は最近使用したものだけです。一覧にない関数を指定するときは、「その他の関数」をクリックすると「関数の貼り付け」ダイアログボックスが開きますので、関数名を選択します。 下図では、関数一覧の「OR」 関数がありますので、クリックします。 |
|
|
|
|
(6) OR 関数の引数を入力します |
|
| OR 関数の数式パレット(下図)が表示されたら、引数編集ボックスに論理式を入力します。 すべての入力が終了したら、数式バーの 2 番目の IF 関数名をクリックして数式パレットを表示します。 この数式パレットでは、「OK」ボタンをクリックしないでください。クリックすると計算式の入力がすべて終了したものとみなされます。 |
|
|
|
|
(7) 2 番目の IF 関数の残りの引数を入力します |
|
| 2番目の IF
関数の数式パレットが表示されると、論理式の引数編集ボックスに
上記で指定したOR 関数が入力されています。 次に、「真の場合」、「偽の場合」の式を入力した後、数式バーで最初の IF 関数名をクリックして数式パレットを表示します。 この数式パレットでも、「OK」ボタンをクリックしないでください。クリックすると計算式の入力がすべて終了したものとみなされます。 |
|
|
|
|
(8) 最初の IF 関数の数式パレットに戻ります |
|
| 最初の IF
関数の数式パレットに戻ると、これまで入力した計算式のすべてが表示されています。内容を確認の上間違いなければ「OK」ボタンをクリックします。以上で終了です。 なお、訂正がある場合は訂正する関数名をクリックすると該当の数式パレットが表示されます。 |
|
|
|
|